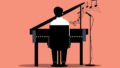ピアノで使われる「コード」とその役割
ピアノの楽譜では、メロディーラインの上に「C」や「G7」などの英数字が記されていることがよくあります。
これらは、特にポピュラーミュージックで頻繁に見られ、メロディーに調和するハーモニーや和音を示すものです。
これらのコードを理解しておくと、ただそれを見ただけで、どのような伴奏を加えれば良いかが分かるようになります。
和音のタイプやその響きを学ぶことで、コードが示されていないクラシック音楽なども、より深く理解することができるようになります。
コード表はしばしば楽譜の初めに載っていたり、オンラインで見つけることができますが、一つ一つ調べるのは時間がかかりがちです。
ここでは、コードの構造や読み方を初心者にも分かりやすく説明していきます。
また、よく使われるコードのカタカナでの表記も紹介していますので、是非チェックしてみてください。
コードの構造とその読み方
私たちが普段耳にしている音階「ドレミファソラシド」は、実はイタリアから来ており、日本では「いろは歌」を使って「ハニホヘトイロハ」と表記されることがあります。
英語圏では「CDEFGABC」というようにアルファベットで表記されます。
例えば、C(ド)を根音とし、そこから三つ数えてミ、さらに五つ数えてソを加えると「ドミソ」の和音、つまり「C」コードが形成されます。
この「C」コードは明るい響きを持っており、「シー」と読みます。
一方で、D(レ)を根音にした場合、ファとラを加えると「レファラ」という和音になり、これは比較的暗い響きを持つため、「Dm」と記され、「ディーマイナー」と読まれます。
コード名は根音を基に定められ、音の高さや順番が変わっても、その和音が持つ特性は変わらないのです。
例えば「C」であれば、「ドミソ」でも「ミソド」でも「ソドミ」でも、全て「C」コードとして認識されます。
メジャーとマイナーコードの基本
ピアノのコードには、その響きによってメジャー(明るい響き)とマイナー(暗い響き)の区別があります。
メジャーコードは、一般的にコード名のみで表されることが多く、例えばCメジャーは単に「C」と記されます。
しかし、マイナーコードには、例えばCマイナーであれば「Cm」と小文字の「m」が付けられます。
Cコードの「ミ」を半音下げるとCマイナーの「ミ♭」となり、一気にその響きが暗くなります。
逆に、Dマイナーの「ファ」を半音上げるとDメジャーに変わります。
これにより、コードのメジャーとマイナーは簡単に変換できます。
以下に、よく使われるメジャーとマイナーコードの一覧を示します。
メジャーコードの例
C(ドミソ)、D(レファ♯ラ)、E(ミソ♯シ)、F(ファラド)、G(ソシレ)、A(ラド♯ミ)、B(シレ♯ファ♯)、E♭(ミ♭ソシ♭)、A♭(ラ♭ドミ♭)、B♭(シ♭レファ)
マイナーコードの例
Cm(ドミ♭ソ)、Dm(レファラ)、Em(ミソシ)、Fm(ファラ♭ド)、Gm(ソシ♭レ)、Am(ラドミ)、Bm(シレファ♯)
「属7コード」の特性と使い方
属7コードは、その不安定さから次のコードへ解決を求める特性があります。
例えば「G7(ソシレファ)」は明るく響きますが、何かに解決したくなるような感じがします。
G7の後にCコード(ドミソ)を弾くと、すっと心が落ち着くような感覚があります。
同様に他の属7コードも、特定のコードに解決することで、音楽に動きを加えることができます。
以下に、いくつかの属7コードとその解決コードを紹介します。
G7(ソシレファ)→ C(ドミソ)または Cm(ドミ♭ソ)
C7(ドミソシ♭)→ F(ファラド)または Fm(ファラ♭ド)
D7(レファ♯ラド)→ G(ソシレ)または Gm(ソシ♭レ)
E7(ミソ♯シレ)→ A(ラド♯ミ)または Am(ラドミ)
A7(ラド♯ミソ)→ D(レファ♯ラ)または Dm(レファラ)
F7(ファラドミ♭)→ B♭(シ♭レファ)または B♭m(シ♭レ♭ファ)
これらの属7コードは、和音の中で不安定さを感じさせ、解決へと導く役割を持ちます。
7が加わると変わる音色:メジャー7とマイナー7のコード
7が付くコードには、メジャー7とマイナー7の二種類があります。
メジャー7は、例えば「CM7」や「CMaj7」と表記され、「シーメジャーセブン」と読みます。
これらのコードは、Cの場合ドミソにシを加えた「ドミソシ」となります。
このシリーズには、FM7(ファラドミ)、GM7(ソシレファ♯)、AM7(ラド♯ミソ♯)などがあります。
マイナー7は、「Cm7」のように表記し、「シーマイナーセブン」と読まれ、例えばCm7は「ドミ♭ソシ♭」の和音になります。
Fm7(ファラ♭ドミ♭)、Gm7(ソシ♭レファ)、Am7(ラドミソ)などがこれに該当します。
メジャー7やマイナー7のコードは、ジャズやポップミュージックでよく用いられ、洗練されたおしゃれな響きを提供します。
複雑さを加える数字のコード
音楽にさらなる深みを加えるために、6、9、11、13といった数字が付加されたコードもあります。
例えば、C6(ドミソラ)はCの基本のトライアドに6番目の音を加えたもので、C9(ドミソシ♭レ)は、さらに9番目の音を加えたものです。
これらのコードはジャズに多く見られ、音楽に豊かなハーモニーをもたらします。
例として、C11やC13のコードは非常に複雑で、ピアノではすべての音を演奏することは難しいため、選択的に音を押さえる技術が必要です。
音の広がりを感じさせるaugコード
augコード、例えば「Caug」や「C+5」と表記されるこれらの和音は、根音から五番目の音を半音上げたもので、これにより和音が広がるような響きを持ちます。
これは、例えば「Caug(ドミソ♯)」から「F(ドファラ)」への移行に使用され、曲中での効果的なトランジションを生み出します。
同様に、GaugやFaugも、次のコードへの移行をスムーズにし、音楽に動きを加える役割を担います。
Caugの場合、その転回形はEaugやA♭augと同じ音を共有しており、これが音楽理論の面白い側面を示しています。
これらのコードは、ピアノの演奏において多様な表現を可能にし、音楽をよりリッチで魅力的なものに変えます。
それぞれのコードを理解し、適切に使用することで、あなたの演奏はさらに深みと洗練を増すでしょう。
緊張感を与えるsus4コード
sus4コードは、ピアノ演奏でよく使われるコードの一つで、「Csus4」などと表記され、「シーサスフォー」と読まれます。
このコードの特徴は、根音から3番目の音(通常はメジャーコードでいうミ)をファ(4番目の音)に置き換えることです。
この変更により、音に一時的な緊張感が生まれ、「戻りたくなる」響きが特徴です。
「sus」は英語の「suspend」に由来し、「吊り上げる」という意味があります。
このコードは特に、楽曲のピークや転調の前に使用され、聴き手の期待感を高める効果があります。
代表的なsus4コードには、Csus4(ドファソ)、Dsus4(レソラ)、Esus4(ミラシ)などがあります。
神秘的な響きのdimコード
dimコード、またはディミニッシュコードは、「diminish」から名付けられ、その名の通り「減らす」または「小さくする」効果を音楽にもたらします。
このコードは、根音から順に三半音(半音を三つ数える)ごとの音を重ねることで構成され、例えばCdimはドミ♭ソ♭ラという構成になります。
このコードの音色は不気味で緊張感があり、サスペンスやミステリーなどのシーンで効果的に使われます。
dimコードは転回しても同じ形の和音が得られる特性があり、例えばCdimの場合、E♭dim、G♭dim、Adimといった転回形が可能です。
まとめ
ピアノで使用されるコードは多岐にわたり、その種類や使い方を理解することで演奏の幅が広がります。
sus4やdimといったコードは、楽曲に独特の感情や雰囲気を加えるために重要な役割を担います。
これらのコードを適切に使うことで、演奏者はより表現豊かで感動的な演奏が可能となります。
コードを学ぶことは時間がかかるかもしれませんが、その努力はピアノ演奏の質を格段に向上させるでしょう。